
-
カテゴリ別 最新ニュース
-
2026-02-17
リリース
国際航業「エネがえるBiz」が宜野湾電設の成約率向上を支援 ~提案資料作成時の試算工数を3分の1に短縮し、根拠あるシミュレーションを実現~
-
2026-01-21
イベント/セミナー
-
2026-01-07
経営/財務
-
2026-01-26
災害調査活動
-
2026-02-27
お知らせ
[独自レポートVol.40]積雪地域の太陽光提案、営業の87%が「難しい」と回答 〜積雪影響を簡易反映できる機能に85%が期待〜
-

カテゴリ別 最新ニュース
2026-02-17
リリース
国際航業「エネがえるBiz」が宜野湾電設の成約率向上を支援 ~提案資料作成時の試算工数を3分の1に短縮し、根拠あるシミュレーションを実現~
2026-01-21
イベント/セミナー
2026-01-07
経営/財務
2026-01-26
災害調査活動
2026-02-27
お知らせ
[独自レポートVol.40]積雪地域の太陽光提案、営業の87%が「難しい」と回答 〜積雪影響を簡易反映できる機能に85%が期待〜
2023/11/10
お知らせ
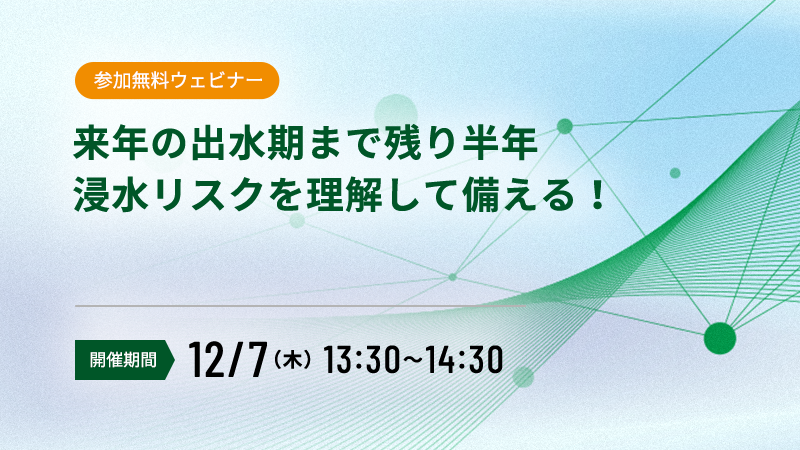
2018年の西日本豪雨、2019年の台風19号、2020年の球磨川の氾濫、2021年の筑後川の氾濫など、近年、水災害は大規模化・甚大化する傾向にあります。この傾向は今後、企業の事業活動に大きな影響を与えることが懸念されます。
そのような水災害の大規模化・甚大化に企業が適切に対応できるように、本セミナーでは、洪水ハザードマップやその他の活用できるリスク情報、解析手法なども含めた水害リスク評価の最新手法を事例を交えて解説します。
*国際航業は、事業の一つとして防災系のコンサルティングサービスおよびシステムの提供を通じて、国や多くの自治体、企業をご支援させていただいております。その一環として「自然災害リスク」に関するセミナーを開催しております。
来年の出水期まで残り半年 浸水リスクを理解して備える!
2023年12月7日(木曜日)
13:30~14:30
Webセミナー
※通信環境のよい場所でご視聴ください。
無料(事前登録制)
国際航業株式会社
・製造業を中心に、水災害リスクがある工場・施設等を有する企業
・工場の施設管理者およびBCPの担当者
過去、自然災害により多くの企業で被害が発生してきました。
特に近年の台風の大型化に伴う水災害の大規模化は、今後、事業に大きな影響を与えることが懸念されます。
<過去の水害による被害額>
2018年(平成30年) 1兆4000億 (例 西日本豪雨)
2019年(令和元年) 2兆2000億 (例 台風19号による長野新幹線水没被害)
2020年(令和2年) 6600億 (例 7月豪雨による球磨川氾濫)
2021年(令和3年) 3700億 (例 8月豪雨による筑後川氾濫)
工場や倉庫など事業場の浸水対策を実施する場合、自治体が公表する洪水ハザードマップで浸水リスクの有無を把握し対策を検討することが一般的です。
しかし、洪水ハザードマップでは浸水深が「0.5m以上3.0m未満」などかなり幅を持った数値しか出ていないため、具体的な対策工には使用しづらい場合があります。
また、「計画規模」や「想定最大規模」といった前提条件の違いによる値の差異や「家屋倒壊等氾濫想定区域」「浸水継続時間」など従来の洪水ハザードマップに加え新たなリスク情報も公表されるようになってきておりますが、その意味が曖昧で分かりにくく対策工に上手く活用できていない場合も多くあるかと思います。
本セミナーでは、洪水ハザードマップやその他の活用できるリスク情報、解析手法なども含めた水害リスク評価の最新手法を事例を交えて解説します。
小宮 賢祐
防災環境事業部 防災ソリューション部 ソリューショングループ
経歴
・300件以上の水害リスク評価業務に従事
・Bois/防災情報提供サービスの開発運用に従事
以下のお申し込みフォームから申し込みできます。
お申込み後、受付完了メールを送付させていただきますので、ご確認お願いいたします。
※同業他社様のご参加はお断りさせていただきます。また定員、その他事情によりお断りする場合もございます。あらかじめご了承ください。
国際航業株式会社 防災環境事業部 フロント営業部
(Mail: kankyo-solution@kk-grp.jp Tel: 03-6327-1987)
このページをシェア